
左 専務 杉井健太郎氏 右 社長 杉井均乃介氏
天保13年(1843年)に創業した蔵元に取材でお世話になりました。
かれこれ180年近く酒造りに邁進されてきたわけですね。
僕がこの酒蔵さんにとても感銘を受けたのが、父から子へ酒造りのこだわりや考えはしっかりと踏襲、吸収され、さらに昇華されていたところです。
気象予報士でもある健太郎氏は世界40各国以上周り、感性を高められ、コンサル会社で培ったノウハウを如何なく発揮されておられます。

杉井酒造では日本酒だけでなく、酢、みりん、焼酎なども造っておられます。
<以下みりんの説明>
・みりんは江戸時代にほぼ確立した本来の製法に従い製造し、水飴等の醸造用糖類等や醸造アルコールは一切使っていません。
・活性炭濾過を行ってません。
オフフレーバーや不要な雑味を除去するために利用されるのですが、一方でそれ以外の香りを除去してしまいます。
飛鳥山では原材料や製造工程に注意を払う事で、オフフレーバーや不要な雑味が生じないため自然で奥深い香りを保持することが可能になってます。
・糖度が高いため、雑菌が増殖しにくく、火入れを行う必要がないため、本来火入れによって失う香りが残っています。
また、熱によって麹由来の酵素が失活せず、栄養素が豊富です。
引用元:杉井酒造
市販の酢やみりんも、もちろんいいのですがたまにはこだわってみると感性に新たな刺激が加わって面白いんじゃないでしょうか?
ちなみにすぐに売り切れちゃうみたいなので要チェックです。

お酢の飛鳥姫
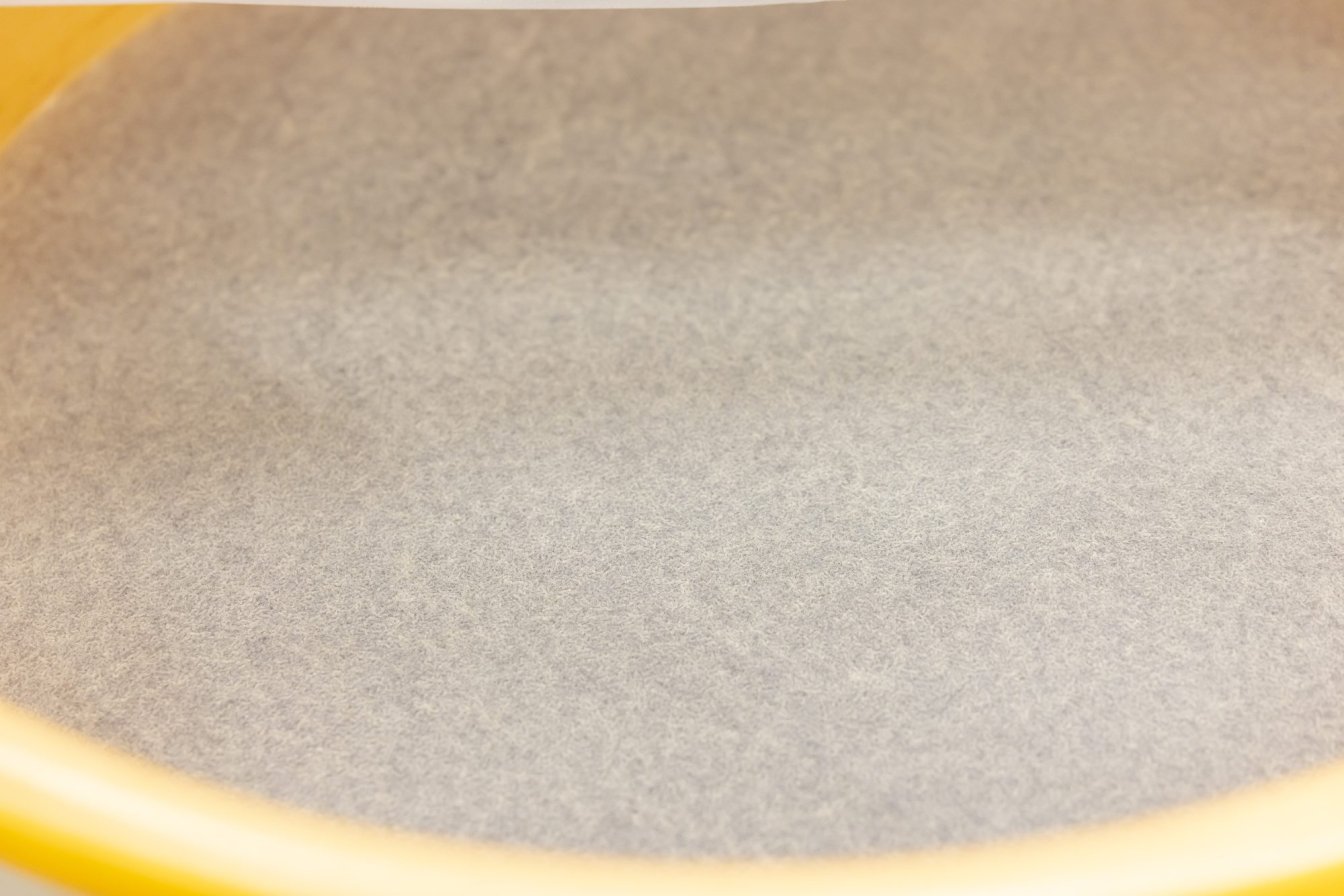
仕込み中のお酢
最後に日本酒の仕込み方法について引用させていただきます。
速醸酛(そくじょうもと)
酛の仕込みにあたり現代では有害な雑菌の繁殖を抑えるために「乳酸」を添加して酛を酸っぱくします。
酢飯や酢漬けものが腐りにくいように乳酸を加えて酸っぱくしておくと細菌の繁殖が抑えられますが、酵母菌は酸性にもかなり耐性があるので酵母菌だけが増殖して高い酵母密度の酒母が完成します。
この乳酸を加えて育てる酒母を「速醸酒母」といいます。
現代の日本酒醸造では、そのほとんどが「速醸酛」(速醸酒母)といわれる方法で造られています。
この方法が最も一般的なので「速醸酛」で造られた酒には特に「速醸酛」の表示はしてありません。
速醸酛の造り方は明治時代に純度の高い乳酸が入手できるようになって考案されました。
日本酒の歴史の流れのなかでは比較的新しい手法です。
生酛(きもと)
・生酛造りは江戸時代中頃に灘(兵庫県)で確立した技法です。
乳酸が入手できなかった明治時代以前に行われていた酛の方法が「生酛」「菩提酛」です。
酛に加える乳酸が無かった時代は、速醸酛より低温に仕込んで雑菌の繁殖を抑えながら自然に乳酸菌が繁殖して乳酸を生産して酸っぱくなるように誘導していました。
乳酸菌は自然界に広く生育していて酵母のように糖分に富む環境でよく増殖します。
繁殖した乳酸菌は酒母工程の後半に酵母菌が増殖してくると酵母の造るアルコールと自らの造った乳酸によって死滅してしまいます。
こうして酵母菌と乳酸を高濃度含んだ酛ができあがります。
明治時代初期までは日本酒の酛は全て「生酛」あるいは「菩提酛」で造られていました。
山廃酛(やまはいもと)
・明治時代に生酛の製法を一部簡略化した方法が山廃酛(山おろし廃止酛)です。
生酛の製造工程には「山おろし」と呼ばれる工程があります。
当時は原料米の精白は低く現代の高精白米と比べ溶けにくいうえに麹菌の力も弱かったと考えられます。
そのため低温での生酛仕込みにあたり、原料米を溶かすために仕込みは小さめのたらいのような桶に分けておこない、これを櫂ですりつぶす作業をおこないました。
この作業を「山おろし」と呼びます。
山おろしは大変に手間のかかる作業です。
明治時代になり原料米の精米も多少良くなったり、麹菌の育種も進んだ事なども影響したのだと思いますが、手間の掛かる「山おろし」を省略しても米の溶解が進み乳酸菌と酵母菌の増殖過程も生酛と同じように進んで健全な酒母ができる事がわかりました。
この方法を「山おろし廃止酛」略して「山廃酛」と言います。
菩提酛(ぼだいもと)
・生酛の原型といわれ室町時代に奈良県の菩提山のふもと正暦寺で使われるようになったと伝わるのが「菩提酛」(「水酛」とも言われる)です。
まず飯を溶かした、生酛と比べて濃度の薄い「そやし水」といわれる液に乳酸菌を生やして酸性水をつくり、これを仕込み水として酛を仕込みます。
生酛が冬季の低温環境下でないとうまく出来ないのに対し、比較的暖かい時期に造りやすく操作も生酛と比べて簡便な事から広く行われていたようです。
江戸時代に生酛を用いた寒造りによる酒質の優良さと安全性が認識されるようになると菩提酛は少数派になりました。
昭和初期くらいまでは使う蔵もそこそこあったようですが現代の酒造の教科書からは姿を消してしまいました。
菩提酛発祥の地である奈良県では近年復刻製造されていますが、奈良県以外で製造しているのは数社のようです。
引用元:杉井酒造
いろんな仕込み方がある日本酒。
お米や水、気候、風土に合わせて酵母や仕込み方を工夫したり、設備や製法に独技を用いたりする蔵人の方々。
話を聞いてるだけで途方もない苦労や研鑽の中に、我々が飲んでいる日本酒があるんですね。
ともかく、ただただ感謝です!

アクセス
東名高速道路ご利用の場合 焼津ICから約20分
電車ご利用の場合 JR東海道線 藤枝駅下車 徒歩20分
休業日:日曜祭日(土曜不定期休みあり)
営業時間:10:00~18:00







